マスクはロマン
小谷:やっぱりその、私はレイヤーなので。
巽:みんなレイヤーってわかる?コスプレイヤーです。小谷さんは日本初と云われているんです、ウィキペディアによればね。
小谷:ジェネレーションが早かったっていうだけで(笑)
コスプレをすると「なんでするの?」とよく聞かれるんです。「好きだから」とか「楽しいから」と言うんですけど、やっぱりそれだけではみんなは真実を語っていないとか言うんですよね。なんか真実が欲しいらしいんですよ。逆にマスクするとどうなのっていうと、私はマスクをするとだいたい人間というのはカッコよくなると思います。そう、かっこいいんですよ。

やはりマスクはロマンです。1番マスクしてかっこいい人っていうと、やっぱりあの『ガンダム』のシャアで。でもマスク取るとかあんまりかっこよくないよね。『機動戦士ガンダム』に出てくるシャア少佐はマスクをしてるとハンサムだけど、マスクを取るとなんかなあみたいな。ちょっとつまらない。超絶感を喪う(笑)
なんかね、パンデミックは嫌なことばっかり多かったし、不自由でもうイライラをしましたね。でも道行く人がマスクをしているとですね、「この人がどうしてこんなに美しいのか」と思うぐらい目が皆さん綺麗でかっこよかったかもしれない。ですので日本人がマスクを取りたくないのは、やっぱりロマンが欲しいって言うか、もっとかっこよく見せたいのかと思うような感じがしないでもないかなって感じます。それで、ロマンっていうのはやっぱりゴシック。生々しい現実というのは美しいとは限らないし、必ずしも垢ぬけているものでもないんですけど、マスクはやっぱり人を垢抜けさせます。本当にそれは何かやっぱり装うっていうかね、ファンタジーだと思うんです。そこはやっぱりファンタジー。だから先生がおっしゃるように何かを暴露するとそこには事実があるはずだ。その真実っていうのはたぶん現実だと思うんですが、現実がその何かを知りたいって思って、みんなマスクを外させようとするんですけども、何もないっていうんですかね。だから真実はないと、やっぱりファンタジーしかなかったんだね。みんなが見たいものしかなかったっていう話に落ち着く。これはなかなか深い話だなと思いますし、それがやっぱりゴシックの本質かもしれない。
巽:みんなが見たい現実しか見ないわけだ。
小谷:なんでマスクを外したがったり暴露したりとか、真実を知りたがるかというと、おそらく人間は誰でも漠然とした不安のようなものを持っていて、言葉を与えたい、それがなんであるか説明したいと言う部分があって。それは1つのファンタジーを作るきっかけになってるんじゃないかなって。例えば、京極夏彦作品を読んでいて思うことなんですが、彼のミステリーの中に精神分析の話が結構出てくるんですよ。それで精神分析的に考えると、こうであるというふうなことを精神分析関係の人に語らせる。だけど、京極堂はそれはファンタジーだと指摘する。それは一つの答えを欲しいから、そういうふうな因果関係をつけているのであって、実際にはあれはまやかしだと言う。これ、結構深いなと。やっぱり不安を解消するための理由付けとしても、何か原因があるとか、だから結果がこうなんだろうという想定に従ってストーリーを組み立てて行くっていうようなことを、かなりやってるんじゃないかなという疑いは捨てきれない。
マスクはやっぱりロマンです。ファンタジーがやっぱり好きなので、マスクいいじゃないかと。やっぱりシャーアにはいつまでもマスクをつけてほしいなあとか思うわけです。「アンマスクド」でマスクを外す。でも、「アンマスクド」されても、マスクの意味っていうのがやっぱ分からないんですよね。マスクとは何だったのかっていうのが分かるところがある。パンデミックでみんなマスク外してふらふら歩いていると、ファンタジーがずれた世界にやっぱりまたいっちゃったかなって気がするんですね。
1つ印象的な出来事があって。マスクのある世界がロマンだって私が思ったのが、ちょうどね、パンデミック最中に私の教え子が結婚したんですよ。それでよばれたので行ったんです。パンデミックのさなかの結婚式だったので、お客さんもね、仲人もね、全員マスクしてたんですよ。マスク結婚式ですね。花嫁と花婿もマスクしてたんですけど、さすがに式の間だけはちょっと外したんです。だから花嫁と花婿以外は全員マスクしてるってすごい異様な類を見ない結婚式でした。しかし私はルパン三世の『カリオストロの城』でのクラリス姫のいかがわしい結婚式をちょっと想像してですね。多分、この人達にとっては忘れられない一生の思い出になるよねって思ったんです。でも高齢者のかたも若い人もね、マスクしていたからみんなかっこよかったです。でね「あー、なんかマスクってもあんまり悪くないな」って思ったんですね。
マスクとマイケル・ジャクソン
細野:私がマスクをしてる人ということで1番最初に思いつくのが、私が中学生の時からずっと好きだったマイケル・ジャクソンです。現在ではよく知られるようになりましたけど、彼は尋常性白斑症という皮膚の色素が抜けてしまう病を患っていたんですね。だから彼に他にどういう意図があったかということまでは定かではないですけれども、少なくとも一部は紫外線の悪影響を受けないようにという目的もあってマスクをしていたんです。布マスクをした先駆的アメリカ人ですよね。というわけで、彼自身は自分が尋常性白斑症、あと全身性エリテマトーデスという障害を持っているっていう事実、つまり何の「ロマン」もない「ファクト」を80年代のかなり早い段階から公表していました。けれども、メディアはそのことには一切注目せずに、彼が「マスク」をしている理由ですとか、あるいはその他の、さまざまなことに勝手にロマンを求めて、つまり、多くの場合はネガティブで過剰な意味を付与していたんですね。彼は、プラクティカルな理由でマスクをしていたのに、彼のマスクやその他の部分に過剰な意味を付与していたのだと、今の小谷先生のマスクはロマンっていうお話を聞いて考えていました。
彼自身が、意図的に装飾性のあるロマンティシズムを帯びたスーパースターとしての自己像を構築するために進んで「マスク」をかぶっていたという面はもちろんあると思います。巽先生と宇沢美子先生監修の『よくわかるアメリカ文化史』というテキストのコラムでも書きましたが、マイケル・ジャクソンの仮面性が象徴的に表れているのが「デンジャラス」という91年のアルバムのジャケットです。

仮面か遊園地の書き割りみたいなものにゴテゴテと動物であるとか、羽の生えた妖精のようなものとか、人の顔とかが描かれていて、その向こうからマイケル・ジャクソンが目だけ覗かせているというイラストが採用されています。その壁、あるいは「マスク」の一部は遊園地のアトラクションのようなものになっていて、それ自体が異世界というかファンタジックな世界を構築しているのです。さらにそこには、映画『グレイテスト・ショーマン』(2017)のモデルにもなった、P・T・バーナムという19世紀前半の実在のショーマンの横顔がなぜか一番前に描かれています。P・T・バーナムという人は人種的な他者ですとか、障害を持った人を「フリーク」として見世物にした人でもあるので、そのP・T・バーナムの顔をおくことで、彼が障害を持った自分の身体を自ら仮面をかぶって、舞台上の見せ物にしているということが自己言及的に現れている、1つの象徴的なグラフィックになっています。
マイケル・ジャクソンにはゴシック的な魅力もあると思っていて、「スリラー」は完全にB級ホラー映画へのオマージュという感じなんですけれども、スリラーのアップデート・バージョンとして作られた97年の「ゴースト」という楽曲のプロモーションビデオは、もっとゴシック的な要素がありますよね。ある村のはずれの城に住むマエストロという人物がマイケル・ジャクソン演じる主人公で、彼のことを村の大人たちは怪しいと思っているけど、子供たちだけは仲良く交流をもっています。けれども、とうとう村長の白人男性がマエストロの住む城に村の人たちを引き連れてきて、「お前はフリークだ」と責め立てます。結局、マエストロはその白人男性を震え上がらせ、子供たちを魅了するダンスを披露し、敵を追い払います。このミュージックビデオはアメリカン・ゴシックの想像力の中、文脈に位置づけられるもので、もうちょっと時間ができたら腰を据えて考えたいなと思っているんですけれども。
私は今までマーク・トウェインで博論を書いてたんですけれども、今現在、巽先生もご著書『アメリカン・ソドム』(2001)で触れられているジョージ・リッパートという19世紀前半の大衆小説作家の研究をしようとしています。彼はエドガー・アラン・ポーとも交流がありました。こういったゴシック的なものへの興味への源流は、私の中ではマイケル・ジャクソンなんです。
『ビジュアル版ゴシック全集』談義
ーありがとうございます。それでは昨年9月26日に出版された『【ヴィジュアル版】ゴジック全集』について伺ってもよろしいでしょうか。
巽:それは私の監訳なので、そこへいたるまでの話をしたいと思います。私のところにそういう仕事が来るようになったのは、むしろ今世紀からなんです。きっかけは、やはり私がアメリカロマン派の研究してるっていうのが1つあると思います。
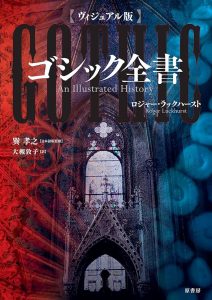
日本のアティーナ・プレスという会社があるんですが、これは中島信彦さんという社長が多分たった1人でやってる会社なんですね。19世紀や20世紀初頭ぐらいまでのすでに版権が切れた、だけど、文学史上の名作を復興、リプリントして1種の全集にして出していくっていうことをよくやっています。ここで私は2005年と2007年に『アメリカンゴシック傑作選』という選集を、第1期と第2期とで出してるんですね。第1期は1820年から60年までで7巻あります。それで第2期が1860年から1940年までで8巻の、つまり全15巻の『アメリカンゴシック傑作選』っていうのを私の監修で出したんです。そこに今回言ったジョージ・リッパードの『クエーカー・シティ』とか『エンパイア・シティ』、それから19世紀にゴシップ的な作品を書いてたジョン・ニール、ウィリアム・ギルモア、シムズ、それから大串先生の専門であるリディア・マライア・チャイルドとか、そういう埋もれた作家たちを復刻しました。2期の方では、『若草物語』で有名なあのルイーザ・メイ・オルコットを復刻しました。彼女は結構ゴシックを書いていて、『モダン・メフィストフェレス』という、それこそスリラーっぽいちょっと怖い話を書いていますね。それからフランシス・マリオ・クロフォード、ピッチジェームズ・オフライン、メアリー・ウィルキンス・フリーマンとか、そういう人たちを復刻して、このシリーズに入れたわけです。それで2009年にポーの生誕200周年ということで、新潮文庫からポーの短編集を2冊ほど出すということがありました。そのため、なんとなくいわゆるゴシックものというと、私が何らかの形で監修とか編集とかすることになっちゃった。
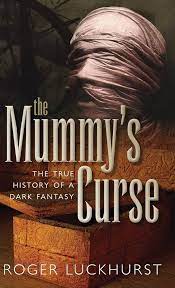
それで今回の『ゴシック全書』のロジャー・ラックファーストですが、彼には、私は以前ドイツの会議で1回会ったことがあります。この人はイギリスの大学で教えていて、非常に目の付け所が良い文学研究書をたくさん出している。ちょうど十年ぐらい前なんですけど、2012年に彼の研究書で私が読んで非常に感銘を受けたのは『ミイラの呪い』という、なんともおどろおどろしい感じがする題がついた研究書です。実際おどろおどろしいですが、ダークファンタジーをめぐる真の歴史っていうサブタイトルがついています。翻訳はないんですけど、これは私が割と一貫して興味持ってる1912年のタイタニック号の沈没というのをモチーフにしている研究書です。タイタニック号の沈没っていうのは、いろんな理由が推測されているんですけど、このロジャー・ラックハーストによれば、あのときのタイタニック号にはエジプト第18王朝の女王ハトシェプストのミイラの棺を運んでいた。だからそのミイラの棺というのが、何らかの呪いを持っていて、それがタイタニック沈没の原因だったんじゃないかと。そう考えると、そのミイラを長く陳列してた大英博物館そのものが非常にゴシック的な想像力を持っているということに迫ってくるんですね。非常に刺激的な見解だったので、十年前の拙著『モダニズムの惑星』(岩波書店、 2013年)でも援用しました。

それから十年後に彼が出したのが、今山下君が言ったこの『ゴシック全書』という本です。大槻敦子さんという方が訳して、私がそれを監修したというかたちです。この『ゴシック全書』はですね、お約束ですから、もちろん、シェリーの『フランケンシュタイン』などが出てくるわけですけれど、従来のゴシック文学史とはもう全然違う、極めて新しい視点がこれでもか、これでもかというほどに登場する。
今日で1番ゴシック的なものはホラーでしょう。いわゆる、ホラー小説とかホラー映画ですね。さらにモンスターが出てくるものまで、ロジャー・ラックファーストは範囲を広げたんですね。だから、なんとあのゴジラも出てきます。
今北米には、中国系のアメリカ人SF作家のテッド・チャンという人がいるんですけど、98年に出した中編の『あなたの人生の物語』という物語があります。2016年にドニー・ビルヴィルヌーヴ監督が映画化した「メッセージ」は、原題は”Arrival”なんですけど、UFOが登場するんですね。これに出てくるエイリアンがものすごいデザインで、上半身は完全にイカとかタコを思わせる類型的なシーフード系なんですけど、下半身がまるで象なんです。だから、その組み合わせが非常に異様なんですね。それでいてかなり本格的というか、サウンドエフェクトが素晴らしい映画になっています。原作とは全然違うんですけれども、それもラックファーストはこの『ゴシック全書』に入れてるんですね。
だからそうなるとエイリアンが出てくるもの、いわゆる日本で言う怪獣映画なども、全部ゴシックになる。そうした視点で、ゴシックの定義を21世紀的に一気に広げた本です。だから監修をしていて、とても楽しかった。邦題では『ゴシック全書』ですけど、原題はGothic Illustrated History。今後のゴシックの定義を抜本的に変えるんじゃないかな。
『テクノゴシック』とゴシック
ーありがとうございます。それでは小谷先生の方から『テクノゴシック』(ホーム社)について、お聞きしてもよろしいでしょうか。
小谷:『テクノゴシック』は2005年に出版された本ですね。どうしてこの本を出したのかというと、
巽:< SFマガジン>で特集やってたよね。
小谷:そうなんです。1992年にゴシック特集というのをやって。というのも、90年前後にゴシックのブームがあったんです、それで「ネオゴシック」とか言われて短編集が出たりとかしていた。でも、なんでゴシックが流行ったのかというと、よく分からないんですね。だけど、流行ってるからとりあえずSFマガジンで特集したんです。
SFの中のゴシックについて考え直そうっていうことで、当時は女性作家ですごいゴシック作家がいると言われてました。1人が、アン・ライス、そしてアンジェラ・カーター。ストーム・コンサンチン。エリザベス・ハンドは後からちょっとゴシック的な要素があると言われました。エリザベス・ハンドはその後、ニュー・ビザンチウムとか言われたんですね。その時に集中的にアンジェラ・カーターとかアン・ライスとかストーム・コンスタンチンの作品を紹介ししたんです。その後、なんとなく気にはなってたんですけど、90年代の終わりぐらいになって、日本で「ゴシック・ロリータ」というのが流行ったんですよ。それで「あれ?」とか思って。ゴシックは、実は90年代に世紀末に向かって全世界的にブームになったんですけど、特にファッションですね。世界的に黒いファッションなどを取り上げたゴシックの解説書が90年代の終わりぐらいに沢山出てきたんです。ポップカルチャーでは、日本も「ゴシックロリータ」だし、海外でも「ゴシックパンク」とか、いろんなゴシックのスタイルがあって。
日本の「ゴシックロリータ」っていうのは本当に世界的に尊敬されてるカルチャーなんです。例えば北欧に行くとゴシックロリータの特集番組とか日本の紹介をやってるわけです。海外に行くと、ゴシックロリータとても好きな人がもう目がハートになって、「すごい素敵ね」とか言ってるんですね。それで「これはどうしてなんだろうな、なんでみんなそんなにも、今ゴシック、そんな黒いのが好きなんだろうと。でもそういえば私も黒いの着てるわ」って。どうしようかなと思ってたら、編集さんから「ゴシックって、なんであんなに流行るんですか?」ということを聞かれて、ちょっと答えられなくて。なんでだろうと思って、集中的にリサーチをして『テクノゴシック』っていうものにまとめることになったんですね。