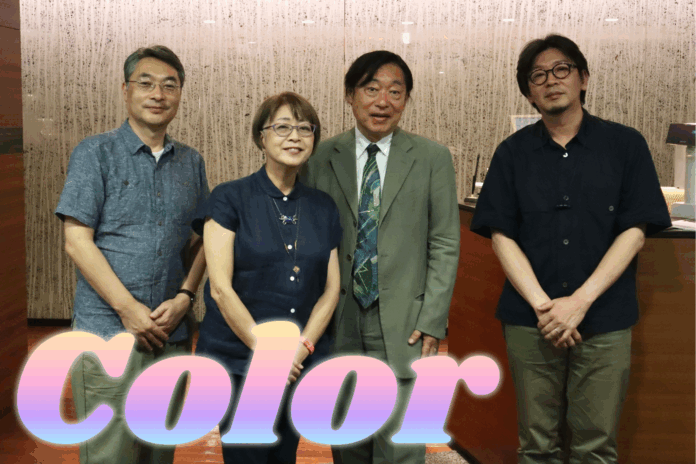世界的米文学者の巽孝之氏、SF&ファンタジー評論家の小谷真理氏のお二人がゲストを招いて討議する名物企画「たつこた鼎談」。今回のゲストは巽ゼミOBで、現在は慶應義塾大学で教鞭を取られている、米文学・ポピュラー音楽の研究者・大和田俊之氏。佐藤光重先生にもご参加いただき、今年のテーマ”Color”を巡って、テーマから想起される作品、Colorの一種としての”Black”、アメリカ文学とアジアン・カルチャーの関わりについて、ご自身の海外生活での経験なども交えながらお話しいただきました。盛りだくさんの内容、どうぞお楽しみください!
本対談は2024年7月に実施されたものであり、記載の内容は当時の状況に基づいています。
本号タイトルColorについて
──本号のタイトルは“Color”といたしました
巽:ブラック・ライヴス・マター以降Colorというのは定番になってきたんですね。それで私は3年ぐらい前にとある雑誌のインタビューで“Black Lives Matter”とは言うけどなぜ”Yellow Lives Matter”と言わず“Asian Hate”と言うのかという話をしました。やはりここ日本の英米文学専攻としてアメリカを考えた場合、Colorという時に必ず黒人が出てきますけどやはりイエローも(出るべきだと)。でもイエローも別に日本人だけではないわけで、そもそも日本の英語教育の祖というとアメリカン・インディアンだったわけですよね。鎖国の末期に日本に流れ着いてそれで北海道から長崎に遣られてそこでペリーが来た時に通訳をする森山(栄之助)とか、そういう優れた通訳を育てたのはアメリカン・インディアンの血を引く捕鯨船員ラナルド・マクドナルドだった。アメリカ文学史(の授業)では触れないのかな。

佐藤:いえ、教えてはいないですね。
巽:日本の英語教育の祖ですよね。その人が「お前の先祖は日本人だったんだよ」と言われて、それでジャパニーズドリームを抱いたわけですよ。我々はアメリカンドリームというものを一応前提にしてアメリカ文学史とかフロンティア・スピリットとか語るけれども、実は日本人がアメリカをちゃんと知るよりも前にベーリング海峡を介在させるジャパニーズドリームがあった。しかもインディアンですからふつうは “Red Skin”のカテゴリーに入れられるけど、おそらくマクドナルドの頭の中ではモンゴロイド的なネットワークということで“Yellow”でも“Red”でもない、たんなる自分の血筋があるのみだったんじゃないかな。逆に言えば、そもそも肌の色という概念そのものが、人工的な言説として作られているに過ぎない。
佐藤:私はブラウン大学のジョン・カーター図書館に2000年に滞在した時にちょうど訪問研究員の入れ替わりでハーバードの院生と会ったのですが、彼がモホークの血をひいていたんです。母方がモホークなのです。彼はNHKの国際放送を子供の頃から視聴するのが好きで日本人にすごく親しみがあったんですけど、それを見ていて自分の母方の人たちの暮らし方と似ているので、子供の頃お母さんに「日本人てインディアンなの」と聞いたことあるそうです。
巽:一気に1980年代中葉にさかのぼってしまいますが、私がコーネル大学のセージ・ホールという学生寮に住んでいた時、一番仲良かったのもインディアンですね。スティーブン・ファッドゥン(Stephen Fadden)といって、今ニューメキシコ州サンタフェにあるインディアン博物館の企画部長を勤めてますが、彼はイロコイ族出身とはいえフレンチの血も混ざっているから、見たところ全く白い。ポストモダン・インディアン文学の大御所ジェラルド・ヴィゼナーも全く白いですよね。それで入学したばかりの私が最初の一学期が終わる頃、マイケル・J・コラカチオ先生の授業のために出したコットン・マザーのペーパーを見せたら、”I hate this guy.”と一刀両断だった。白人としか見えないインディアンでも、植民地時代以来のピューリタンによる異民族虐待の歴史が刷り込まれてますから、Caucasian hateみたいなのがあるわけですよ。だからそれは非常に強烈でしたね。本人はもう白人としか見えないのにやっぱりそういうことで。なかなかギターが上手くて、「エンジン」と「インディアン」を引っ掛けた「インジャンズ」(Injuns)というロックバンドをやってて、時々町中のクラブに出演していました。だからやっぱり今Colorというと当然黒人と思われがちだけど、モンゴロイドという時に少しそのカラーが曖昧になる。そんなに明確に白とか黒とか赤とか黄色とか分けられない。最近はオリンピックの選手とか日本人の名前だと思って見ると、見た目は完璧に黒人だったりと、本来の人種と肌の色が一致しない人がどんどん増えてきている。だからColorというのが一義的ではなくなってきたという感じがしますね。
──小谷先生はこのColorについて、何か想起される文学はありますか
小谷:いつもここでボケることが期待されているようなんで、全力でボケますが(笑)
今年のボケはColorと聞くと、「総天然色」かな。聞いたことあります?総天然色って。

佐藤:昔の映画『天地創造』(ジョン・ヒューストン監督、1966年公開)の広告に書いてあるのを古雑誌で見たことがあります。
小谷:昔映画とかテレビてみんな白黒だったんですよ。それがカラーになった時に日本語訳で「総天然色」て。
佐藤:いまではわざわざ断るまでもない、いろんな似たような言葉で「純」喫茶とか。
大和田:総とか天然とか何か修飾すればいいみたいな。
小谷:だからColorと聞いて総天然色って。
佐藤:Colorはとっても大事なことなんだって感じですね。
小谷:モノクロなのか総天然色なのかっていうと、総天然色の方が未来系というか新しいわけですね。それで白黒はやっぱり古いと言わんばかりですよね。それを小学校の時に刷り込まれてしまった。そこで私は喜んでカラーで『リボンの騎士』を見ました。
佐藤:やっぱり世界を見る時の解像度がグッと(上がる)。
小谷:そうそうそう。モノクロだとね、灰色にも色々あってこれは赤だよねこれは青だよねっていう灰色があると気がつくわけです。で、それに慣れ切ったアタマで、ある日怪獣映画を見たら、あまりの衝撃で。映画に色がついてる!とか言って興奮したことを思い出したんですけど。
大和田:確かに、今の真理さんの話は僕の後の話とちょっと関係してるかもしれないですけど、グレーを見て、これが赤のグレーなのか緑のグレーなのかみたいなちょっとした想像力を求められちゃうところはありますね。

小谷:そうなんです。後付けだけど、白黒だとやっぱり非常に対立がはっきりしてる。言い方なんですが、実は両者の間はさまざまな灰色。それで理解するしかないっていうか、実は脳が勝手に修正している。つまり総天然色になるとモノクロの間には、カラーに変換されるさまざまな灰色があったと気がつくわけです。私はもうフェミニズム第3波に属する人間なので、SFの世界でも、そもそもやっぱり白でも黒でもない中間地帯の話がすごく多いことが気になるの。割り切れないっていうところに住んでる人たちが逃げ道を探すっていうストーリーがSFとかファンタジーに多いしそれがものすごく気になる、惹きつけられる。またエドガー・ライス・バローズの話をしますが、『火星のプリンセス』という話があるんですね。南軍の負けた大佐のジョン・カーターが幽体離脱して火星に行く話で映画になってます。そこで出会う火星人は「赤色人」て書いてあったんです。それでもちろんモノクロの挿し絵で見てるので全然普通の王女様の絵とかで、しかも武部本一郎画伯のハリウッド的なすごく魅力的な絵で書いてあって外国の方々なのかなって思うけど、文章を読むと「赤色人」とか「緑色人」とか出てきてなんだこりゃ、赤色人の絶世の美女?どんなだよ(笑)。
大和田:それはやっぱり先住民に対するなんとなくの仄めかしがあって火星人と微妙に重ねている。
小谷:あっ、そうそう。火星って赤色人、黒色人、緑色人が戦ってる世界。緑色人は顔が昆虫みたいで巨大で手が4本ある。一方ジョン・カーターは白人で南軍の大佐で。
佐藤:南軍の。
小谷:南軍のですよ、南北戦争で負けたほうですね。それでしょうがなくてもう行き場がないからゴールドラッシュでの波に乗り黄金を掘り当てようと、馬に乗って西部に向かってる最中に洞窟があった。そこに髑髏があってねーー絶対あれはネイティブ・アメリカンの何かなんですよーーそこで寝ると幽体離脱して火星に行くっていうイントロです。火星は赤色人・黒色人・緑色人が戦ってる世界でここで想定されてる世界はだいたいローマ帝国みたいな感じ。裸に近い格好で剣持って戦ったりするわけね。で、なぜか銃がないのよ。ジョン・カーターは「比類なき美女」である赤色人の王女様をゲットして、逆玉の輿で登り詰めるわけです。その後黒色人と緑色人の間を調停して大元帥になるわけです。つまりは白人がトップでその下に赤色人とか緑色人、このいろんな種族が仲良くみんなで共存する。
大和田:そこは別にカースト的なものはないんですね。
小谷:王政だから奴隷とか召使はいますね。むかしのローマ帝国みたいな感じかな。それがローマ市民のようにより集まっているからそのトップに上り詰めるのが大変です。ちなみに白い生物も出てくるんですが、白人ではなく大白猿という猿なんですね。それは全然言葉が通じないので凶悪なんです。ただただ暴れてるっていう怪物。そんなエドガー・ライス・バローズの<火星>シリーズ、その時はもう夢中で読んでたけど……今振り返ってみるとこれ赤色人って絶対レッドスキンのネイティブ・アメリカンですよね。宇宙で一番美しいと言われたそのデジャー・ソリスっていう赤色人のお姫様は赤色人でしかも卵性なんですよ、卵を産むんですよね。それでその卵はだんだん大きくなっていって、成人と化したものが生まれてくるっていう今考えると実に変な設定だったな…もう本当にワクワクするような冒険物なんですけど、けっこう偏見からくる猛烈なイマジネーションが炸裂していたかもしれないです。
巽:だから火星がアメリカ西部のフロンティアなんだ。
大和田:そっかそっか。
巽:その影響を受けてるのがブラッドベリの『火星年代記』。
小谷:そうですね。
巽:あれも絶対ネイティブ・インディアン的に火星人のことを書いてるわけですよ。だから絶対バローズに影響受けてるよね。
小谷:ブラッドベリの場合は、滅び去った種族みたいに書いてましたね。そっかー、居留地で生かされていることすらなく、もはや過去という幻想世界にしか生きてないのか、と。
巽:北海道のSF作家:荒巻義雄さん、川又千秋さんは塾員ですけど、火星モノをたくさん書いてる理由は、やっぱり北海道の中に火星を見てるんじゃないか。
小谷:アメリカSFと北海道SFって構造が近いかな、と思ったことはあります。まあ本土人の妄想かもしれませんが。とはいえ、なんかバローズが書くと西部だから温かいっていうイメージだけど、北海道だと寒いですよね。同じフロンティアでも北と南にイメージが分かれるかな。
巽:でも我々がいるニューヨークあたりは(緯度でいうと)大体青森ぐらいでしょ。
小谷:弘前と同じぐらい。話をもどすと、なんかSFってやっぱりそういう風に赤とか黒とか緑とか多種多様なエイリアンが色々出てきて、やっぱりモノクロじゃなくて総天然色的な想像力なんじゃないのかな。フェミニストの第3波的な感性だと中間はどうするのという問題がつねに気になる。この中間っていうのも女性の中でも例えばレズビアンがいるとか、女性の中でも黒人の人はどうしたの?とかモノクロ世界を混乱させる中間地帯をどう考えるのっていう第3波的な問いかけになっていく。
佐藤:インターセクショナリティ。
小谷:そうですそうです、後にそう言われるようになる人たち。でも当時はまだそんな言葉もなかったから手探りでしたね。分からない。例えば女性作家でジュエル・ゴメスが書いたThe Gilda Stories(1991)というお話では、ブラック・レズビアン・ヴァンパイアが出てくる。黒人で女性でレズビアンで吸血鬼ですよ。主人公ギルダは奴隷農園の少女で、ストーリーは、三重に阻害されているけど、そのなかで、自分たちのアイデンティティをどういう風に考えていくかとかをサバイバルする姿を通して描いている。読者的には、三重の抑圧ってまず想像できないので、まずそれがどういうものかを読書体験する。この子はまず奴隷農園から逃亡する。10代の女の子で黒人の子の価値評価はもうモノとしてしか見られることがない奴隷です。それで逃げ込んだ先でネイティブ・アメリカンの女性に会うんですけど、それがたまたまヴァンパイアだった。それで彼女に引き入れられて、吸血鬼の世界に入っていく。そこはすごい同性愛的なカルチャーです。ヴァンパイアは人間とは全く違った形で仲間を関係なく増える種族なんですね。異性愛とあまり関係なく増えていくから同性愛的な世界として描かれている。ヴァンパイアの世界にはとにかくいろんな人がいると。老人もいれば若い子もいるし、白もいれば黒もいるし、同性愛者もいて雑多なんですよね。だから命は救われるわけだけど、ヴァンパイアてすごく長生きで、18世紀ぐらいから近未来まで生きるんだけど、未来に行っちゃったらヴァンパイアがバイオサイエンスの対象になってしまう。長生きの遺伝子を持ってるから今度は逆に命をつけねらわれて…そういう話になってくるの。それと同時にヴァンパイアであるっていうことで、血を吸うときに相手の記憶が入ってくるんですね。だからそれを物語化して劇作家になったりする。
大和田:すごい具体的なものが書けますね。
小谷:三百年くらいのことなので、盛沢山ですね。いろんな話が出てくる。権力関係の上下も簡単ではないですね。なので、あの本は90年代の代表的な第3波フェミニズム関係ではよく論じられました。まさに総天然色なお話です。
ワシントン・アーヴィングと”Color”
巽:赤色人というのが出たのでちょっと補足すると、これはアメリカ文学史の教科書ででは常識に属しますが、一応復習しておくと、原典講読でワシントン・アーヴィングの「スリーピーホローの伝説」“The Legend of Sleepy Hollow”をやる時にイカボッド・クレーン(Ichabod Crane)とブロム・ボーンズ(Brom Bones)の対決を軸にしますね。非常に便宜的にイカボッド・クレーンっていうのはニューイングランド系のインテリだからペイルフェイス(pale face)、ブロム・ボーンズっていうのは一応体育会系だからレッドスキン(red skin)だという風に図式化するのは、フィリップ・ラーヴが編み出した方法で、これはとても便利なので授業ではそういう風に教えるのが一応王道というか、わかりやすい。だけど最近、今住んでるニューヨーク郊外パーチェスは、アーヴィングの家のあるタリータウンの近くなので、改めて再読してみると、そもそもブロム・ボーンズって本名じゃないんです。本名はエイブラハム・ヴァン・ブラントというオランダ系で、筋骨隆々たる暴れん坊だから「ブロム・ボーンズ」が渾名になってる。それで奪い合う女の子の名前もカトリーナ・ヴァン・タッセル(Katrina Van Tassel)でこれもオランダ系なんですよ。そうなってくると、本当は主要登場人物は全員ペイル、すなわち白人なので、別にブロム・ボーンズはインディアンでもなんでもないでもない。ただしこの点については、ニューヨーク学院で今“Tricultural” Lecture Serieというのでいろんな学者や作家、批評家を呼んでるんだけど、昨年 2023年3月にはメルヴヴィル研究の大家ジョン・ブライアントに講演してもらったので、彼のあの分厚いメルヴィル伝全二巻(全三巻予定)を全部通読したところ、一つ発見したことがありました。
佐藤:慶應図書館では冊子とWeb版両方読めるようになってますね。
巽:やっぱりさすがだなと思ったのは、メルヴィル系の母方がニューヨークのオランダ系、父方がニューイングランドのフランス系という伝記的事実に対して、ジョン・ブライアントは「これは明らかに人種的のみならず文化的な雑婚」と断言していることです。少なくとも日本人から見たら白人同士としか見えないけど、実はアランのニューイングランド・ピューリタン系フランクリン主義とマライアのニューヨーク・オランダ改革派教会的精神の違いもあるし、だからこれは雑婚だというわけだ。
佐藤:クレヴクールの時代の感覚ですね。
巽:そうそう。そうすると例えば最大の失敗作と言われる『ピエール』の読みが関わってくる。だからハドソン川沿いには思いのほかオランダ系の地名が多い。ワシントン・アーヴィング邸「サニーサイド」は、特に秋に訪れると、もう完全にハロウィン仕様になっていてアーヴィングの世界にはぴったりなんです。
小谷:大和田さんと三人で昔行きましたね。
大和田:そこでアフリカ系の最初のお祭りが開催されたという。
巽:そうそう。ピンクスター音楽祭 Pinkster Festival ね。あれもニューヨーク行ってからもう1回行きました。毎年場所が違って去年はオールバニでやった。
大和田:なんか不思議な音楽でしたね。昔の17世紀のままのアフリカ音楽をそのまま伝えてるから、全然ジャズでもブルースですらない。ミンストレルショー以前。面白いですよね。
巽:そうそう、ちょっと面白い。メルヴィル文学におけるアフリカ音楽の研究も最近進展してるからね。ピンクスター音楽祭も毎年開催地を転々としていて、しかも年1回ではない。
大和田:そうなんですか。
巽:5月になると毎週どこかでやってる。大和田くんと一緒に行った時は2009年で、これは行くしかないっていう。
大和田:貴重な経験を。
巽:あの時は開催地がタリータウンだった。
巽:ところでピンクスター(Pinkster)と聞くと、それこそ色彩としてのピンク(Pink)がたちまち思い浮かぶかもしれませんが、これ、実は「ペンテコスト」“Pentecost”(聖霊降誕祭)を指します。明らかにピンクとか桃色を思わせるのに、語源はギリシャ語で5を表す「ペンタ」(penta)で、五音音階(ペンタトニック)などはよく知られています。ピンクスターの場合は、復活祭から 50日目に聖霊が降誕する記念日、五旬節(Pentecost、 Whitsuntide)が訛ったもの。ユダヤ教だと、過越の祭りの二日後から50日目で、モーゼがシナイ山で神から律法を授かった記念日ですね。それがアメリカに入ると、オランダ系の記念祭に黒人系=アフリカ系の音楽が混じるようになった。そういうことを考えると、音楽祭ひとつ取っても、単純な色彩ではない。我々から見て白人に見えても、その白人の結婚は実は雑婚だと言われることもある。だからそういう風に「色」と言っても一枚岩ではなかなかいかない。
“Color”の中の“Black”
大和田:今回の鼎談のテーマがColorと伺って、最初に先生がブラック・ライヴス・マターの話をされましたが、僕はブラック・ライヴス・マター運動が再燃した2020年はちょうど10年ぶりのサバティカルでアメリカに滞在してたんですよ。家族で3月8日に渡米したら、翌日ロックダウンが宣言されたという。1年間ハーバード大学の建物に一度も入れずに帰ってきました。でもあの年の5月にジョージ・フロイドが殺害されて、11月に大統領選挙があって、それで翌年1月にバイデンが就任するという。全部アメリカで経験したんですが、基本的にはずっと家の中にいました。
その時、巽先生の退職記念論文集に寄稿する論文を書かないといけなかったんですが、図書館が空いてないんですよ。でもさすがハーバードと思ったのは、文献や資料がどんどんデータ化されたんです。ものすごい勢いでデータベース化が進んで、リモートでも見られるようになっていく。僕はハーバードの敷地内のレジデンスに住んでいましたが、結局コンピューターの小さいディスプレイ上で文献を漁ってました(笑)。
それで何の論文を書いたかというと、万延元年の遣米使節で咸臨丸が行ったときのことを調べていて。あの時、実は咸臨丸はポーハタン号の護衛艦だったんですけど、そのポーハタン号は西海岸から東海岸に回ってニューヨークにも上陸する。1860年なので、多分東海岸では東アジア系を見るのが初めての人も多かったと思うんですよね。
巽:福澤先生も同行してるけど、あの時、 1860年の段階では東海岸にまでは付き添わず、サンフランシスコ上陸した後、帰国してるんです。
大和田:その当時、現地ではミンストレル・ショーが興行としてあるわけですが、その中に「ジャパニーズ・トミー」という芸名の芸人がいるんですよ。ジャパニーズ・トミーは南北戦争前からミンストレル・ショーに参加していた二人のアフリカ系アメリカ人のひとりと言われてるんですよね。その人がなぜジャパニーズ・トミーと名乗るようになったのかということを考えました。これは仮説なんですけど、遣米使節団の中に立石斧次郎という通訳がいて、この人が現地でものすごい人気になるんですよ。アメリカにおけるアジア系男子の人気という意味では、今のBTSのルーツともいえるような。
巽:ジャポニズムすら存在しない頃だったから、新鮮だったでしょう(笑)
大和田:ジャパニーズ・トミーはあらゆる新聞でもてはやされて、通訳だからちょっと英語もできたんですよね。彼の周りに女の子が群がっちゃって、その流行に乗じて「Tommy Polka」という曲もリリースされる。
小谷:日本という属性がなにかのチャームポイントになったのかしらね(笑)
大和田:そのことをずっと19世紀の新聞データベースで調べていたんですが、ジャパニーズ・トミーは元々違う名前で活動していたのが、どうも1860年の日本の遣米使節の流行にあやかって「ジャパニーズ・トミー」という芸名にしたようなんですよね。確たる証拠はないんですが。彼は小人症で背が低くて、それも「ジャパニーズ」と名乗る根拠の一つになっているような気がするんですが、要するに、今、先生と真理さんがおっしゃったように、黒人なんだけど「ジャパニーズ」と名乗る、でもまだアメリカの東海岸では「アジア系」はまだマイノリティとしても知られていないんですよね。そうすると、メディアなどでは最初は黒人と同じように描写される。それが徐々に“slant eye”のように、マイノリティーの記述が分節化されていく。黒人を描写する記述から黄色が分化されていくんですよ。立石斧次郎とジャパニーズ・トミーの2人の出会い/出会い損ねに、アメリカにおける東アジア系のイメージ形成の過程を見ることができる。たとえば立石斧次郎の描写のひとつに「歩き方がシャッフルっぽい」という記述があるんですが、シャッフルはミンストレル・ショー由来の「すり足」のことで、アフリカ系アメリカ人のステレオタイプとして定着している。だから最初は立石斧次郎の歩き方も黒人のステレオタイプに合わせて描写されるのが、そこから少しずつイエロー独自の描写/記述が出てくるんです。
19世紀に中国系移民が西海岸に到着すると、ミンストレル・ショーでは「チャイナマン」という中国系のキャラクターが登場しますが、もともとミンストレル・ショーには「ジム・クロウ」や「ジップ・クーン」などの黒人キャラクターが存在していましたよね。興味深いのは、ステージ上では最初の頃、黒人キャラクターを表す音楽と中国系の「チャイナマン」の音楽が同じだったみたいなんですね。クロマティシズム、いわゆる半音階を中心とする旋律とかシンコペーションとか、そうした黒人を表す音楽的特徴もすべて「チャイナマン」にも当てはめられたと説明されています。実は2010年代に入ってからカラーライン研究、つまり人種をめぐる「線/線引き」の研究なんですけども、それと音や音楽を関連させる研究がたくさん出てきたんです。例えば19世紀後半から20世紀にかけて「レコード」という新しいメディアが出てきますが、レコードはミンストレル・ショー(舞台)と違って音だけで流通するので、そうするとミンストレル・ショーでは白人の芸人が顔を黒塗りにして黒人のモノマネをしていることがわかるけど、レコードだと「顔がない状態の音だけで」黒人であることを証明しないといけない。それが、3度と5度と7度の音をフラットさせるブルースの音楽的特徴として定着したのではないかという研究もあるんですよ。
巽:あぁなるほどね。
大和田:メディアが変化し、人種の「色」をいかに音だけで表現するかという問題が生じたというか。おそらく最初はイエローもブラックも一緒に扱われたと思うんです。あとこれは先生にもお聞きしたかったんですが、一般的に例えばブルースのペンタトニックスケールといわれますが、西洋音楽史でいうと完全にドビュッシーの中国趣味ですよね。黒人のブルースのペンタトニックスケールと、ドビュッシーの印象派周辺の中国趣味がなぜ重なるのか。
巽:ドビュッシーは「ゴリウォーグのケークウォーク」(1908年)で黒人系ラグタイムのリズムを取り入れたのは有名ですが、もともとホールトーン・スケールが得意ですよね。逆に言うと、黒人音楽を再解釈したドビュッシーからのちのセロニアス・モンクやリチャード・ティーが生まれたと言っていい。一方、彼の「塔」(1903年)などのペンタトニック・スケールは、これはもうYMOとしか言うほかない。
大和田:印象派とのイメージの重なりは、実際の交流や影響関係をもとにしているわけですが、そうした人種と音の関係が、少しずつ解像度があがるにつれてブラックとイエローの違いが際立つようになるのでしょうね。これはあくまでも白人からみたイメージということですが。
巽 :3度、5度をフラットさせるディミニッシュ・コードを駆使したジャズの名曲も「ストーミー・ウェザー」とか、少なくないから。
大和田:なるほど。
巽 :そう言えば、私が高校生の頃、1970年代前半に毎週よく見ていたテレビ番組に、ドン・コーネリアス司会の「ソウル・トレイン」があったんですよ。スティーヴィー・ワンダーやクール&ザ・ギャング、コモドアーズのファンクはその番組で知ったんだけど、「ブルー・アイド・ソウル」(Blue Eyed Soul)という曲がよく流れていて、とにかくカッコいい曲だった。アヴェレージ・ホワイト・バンドの当時のヒット曲「ピックアップ・ザ・ピーシズ」(Pick Up the Pieces)があまりにカッコいいので、音楽ジャーナリズムにもあんまり親しんでなかったから、それがドラムス以外全員白人スコットランド人のスコティッシュ・ファンクだったなんて、全く知らなかった。つい最近ビデオで見たら、スコットランド人ギタリストがタータンチェックのキルト姿でファンキーなリズムを刻んでるのにびっくり。考えてみれば、エルビス・プレスリーだってザ・ビートルズだってゴスペルの影響受けてるわけだから、当然といえば当然なんだけど、高校時代はまずは楽曲ありきだったから、まだ人種の概念が育っていない。今から振り返ってみれば、その頃起こっていた文化混淆が今日まで来ている。
大和田:あと人種と音のステレオタイプの関係でいうと、平行四度とかも「オリエンタル」なイメージで語られますよね。そしてこれも、たとえばモード奏法を編み出したマイルス・デイヴィスが、ある意味で西洋的な機能和声から離脱するために三度堆積ではなく、四度堆積和音を多用したことと重なると言えば重なります。これもアフリカン・アメリカンとアジア系の文化的/イメージ的に重なる部分と、そこから枝分かれしていく部分の例と言えるかも知れません。
巽 :日本にも関西を拠点にしたウェスト・ロード・ブルース・バンドがあったでしょう。塩次伸二とかカリスマ・ギタリストだったでしょう。キング・カーティスの「メンフィス・ソウル・シチュー」のバーナード・ パーディ版をさらにアレンジして「京都ソウル・シチュー」って曲に編曲していた。黒い瞳のソウル、というわけですよね。アメリカに渡って活躍している日本人ミュージシャンも増える一方。ニューオーリンズで暮らしているギタリストに山岸潤史がいる。
大和田 :現地で最も認められた日本人ミュージシャンの一人ですよね。
巽 :私が一番最初にアメリカに行ったのはアメリカ建国200周年の1976年の時で、その時やっぱりロックとかジャズとか好きだったから、ジェフ・ベックがちょうどWiredとかなんか出した頃だったんでサンフランシスコでライブ見て、あとロスでオルガン・ジャズのジミー・スミスも聞きに行ったんですね、そしたら同じサンフランシスコでエルヴィン・ジョーンズが出演していて、そのバンドで活躍していたのが日本人ギタリストで川崎燎。楽屋で話しかけたら、もう日本には帰るつもりはないようだったけど、げんに最後はエストニアで音楽活動を続けて惜しくも2020年にお亡くなりになる。
大和田:アメリカで活動した日本人音楽家の先駆者としては穐吉敏子さんがいらっしゃいますよね。
巽:そうそう、ああ穐吉敏子さんはもっと早いですね。日本人初のバークリー音楽院卒業生でしょう。1956年、私が生まれた翌年にはもう渡米してますから。
大和田:イエロージャズの創始者というか。
巽:穐吉敏子って、当時は着物着てジャズ弾くんですよ。
大和田:でもやっぱりあの時代、向こうでも例えば尺八使ってジャズやるのがちょっと流行ったりして。
巽 :ちょっとジャパネスクを入れる。だからレコードで聞いただけじゃ何人がやってるか分からないのが。
大和田:確かに尺八が入ると日本らしく聞こえるんですよね。
巽:ニューヨーク学院の音楽の先生でパーカッション専門のトッド・アイスラーなんかは、もうリーダーアルバムも含めて六枚も出してる上に、理論書も刊行してますが、尺八が入ったりインドのリズムを使ったり多彩ですね。その分、ニューヨークの日本人ミュージシャンとの交友も厚いらしい。
大和田:演奏の仕方はフルートに似てるんですかね。割とカジュアルにみんな尺八を使う。誰か師匠的な立場の人がアメリカで尺八を広めたんでしょうね。
巽 :尺八ジャズね。ありますよね。
大和田:ちなみに先生のお弟子さんもたくさんいますけど、僕は先生の主著のうち「プログレッシヴ・ロックの哲学」を受け継ぐ唯一の弟子だと自負しています(笑)。
アメリカ文学とアジアン・カルチャーの関わり
──2021年に執筆なさった『アメリカ音楽の新しい地図』(筑摩書房)についてお話しいただけますでしょうか
大和田 :これは後書きにも書いたんですけど、元々はトランプが2016年に大統領に当選した時に、元青土社で今は筑摩書房の編集者の方に、「トランプと音楽の話題で3回のコラムを書いてくれ」と言われたのがきっかけです。それを書いているうちに、もしかするとこれは本になるテーマかもしれないと思って、ウェブ連載させてもらうことになったんです。この本はそれをまとめたものですが、最後の2章は2020年のサバティカルでアメリカ滞在中に書いたもので、ちょうどコロナ禍の5月にジョージ・フロイトが殺害されてブラック・ライブス・マター運動が再燃して。あのとき興味深かったのは、K-POPファンがインターネット上でブラック・ライブス・マター運動への連帯を表明したんですよ。たとえばデモの最中に略奪行為を目撃したら警察に報告してほしいとダラス警察が告げ口(スニッチ)を推奨したことがあったんですが、それに対してK-POPファンがそのダラス警察の窓口にBTSの動画を大量に送り込んで機能不全にさせちゃうとか。これってよく考えてみると、テクノロジーを用いて警察権力の強権性を奪うという意味ではサボタージュの定義そのものじゃないですか。ブラック・ライヴス・マター運動の大きなテーマのひとつは警察の残虐行為(police brutality)だったので、インターネットの時代にK-POPファンがアフリカ系に連帯を表明して、サボタージュ的な手法を用いて警察権力に対峙するという。アジア系とアフリカ系の連帯は、アメリカの歴史を丁寧に振り返るとなかなか難しい側面もあるのですが、非常に興味深いなあと。
巽 :今BTSって聞く人はBSTは知ってるのかな。
大和田 :知らないと思います。ブラッド・スウェット&ティアーズという1970年代のブラスロックバンドですよね。でもBTSにも”Blood Sweat&Tears”という曲があるんですよ。ややこしい。
巽 :で、最近BSTのドキュメンタリー映画ができたらしい。ものすごいヒットしたスピニング・ホイールとかファンキーでしたよ、ブラス・ロックの傑作。シカゴはみんな覚えてるけど、BSTをみんな忘れちゃう。
大和田 :BSTの方が、割と通好みでしたね。
巽 :ちょっと黒っぽかった。
大和田:シカゴの方がチャラい。
巽:シカゴはなんか文部科学省推薦みたいな。ウケがよかった。
大和田:そのBSTではなく(笑)BTSが本当ににすごくて。そもそもアメリカのカルチャーをみてきてアジア系の男子に黄色い声援が飛ぶのって、それこそ立石斧次郎以来じゃないでしょうか。
巽 :だからその間にでもYMOとか。
大和田 :YMOもたしかにヒットはするんですが、結局ビルボードのシングルチャート最高位60位ですからね。現在のBTSとは比べられないかもしれません。当時、チャートでいうと多分ピンクレディーの方が上位に上がってますよね。
巽:白人以外をアイドル扱いするのは珍しかった。
大和田:しかもやっぱりアジア系の男子って牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけたナーディーでオタクなステレオタイプがあったから。
巽 :宇沢美子さんが研究している世紀転換期のジャポニズム、転じてはオリエンタリズムですね。
大和田:そういえば今、SFの領域でもアジア系って盛り上がってますよね。
小谷:そうですね。今は台湾SFや中国SF、それに韓国SFってすごく人気があって。『三体』とかね。
巽:女性作家もすごく進出している。
小谷:ハオ・ジンファン(郝景芳)っていう素晴らしい作家さんがいます。あと、韓国系でキム・ボヨンとか。
巽:ハオ・ジンファンの『折りたたみ北京』は傑作。
大和田:英語で書いてるんですか。
巽:自ら英語で書く場合もあれば、翻訳家を介する場合もある。
小谷:英訳したのはケン・リュウだよね。
ケン・リュウが持つ先進性
巽:そう、ケン・リュウがとにかくすごい。アメリカ育ちのテッド・チャンなどとは違って、中国本土出身のカリフォルニア育ちなのにハーバード大学を出てもう完璧なバイリンガルで、弁護士兼コンピュータ・プログラマー、その上作家。自分の作品も短編小説「紙の動物園」でヒューゴー賞、ネビュラ賞、世界幻想文学賞の三冠達成したりしてるのに、そこに安住することなく、さらに友達の作品を訳す。そのうちのひとつが郝景芳の「折りたたみ北京」であり劉慈欣の『三体』。ノーベル賞作家カズオ・イシグロは長崎出身ロンドン育ちだけど翻訳にまで手を伸ばすようなバイリンガルではないし、わが村上春樹もアメリカ生活は長いけど翻訳するのは英語から日本語への一方向のみ。ところがケン・リュウは中国語でも英語でも自由自在、しかも自作のみならず中国SFの世界的普及にも熱心という使命感が強いところが、一味も二味も違う「すごさ」なんです。まさに21世紀の世界文学者ですよ。
小谷:ハオ・ジンファンもそうだよね、ケン・リュウが翻訳してヒューゴー賞とかとった。
大和田:やっぱりなんか中国的な独特の想像力ってあるんですかね。
小谷:新時代という感じがしますよ、確かに。我々にはお馴染みの旧態依然としたお話ではなくて、もっと今風の、インターネットGoGoみたいな新鮮さがある。英米圏にはない独特の雰囲気があるし、一方昔の中国っていう感じでもない。昔の中国ものってやっぱりちょっと鎖国的な閉塞感があったと思うんですけど、ポスト文革ポスト天安門っていうのかな。もうすこし資本主義的な要素があるかな。今の中国のグローバル対応で。
巽:洗練されてるんですよね。
小谷:世界文学として洗練されてる。ちゃんと世界の状況をよく知ってて書いてますね。ケン・リュウの小説も、あの人はアメリカに移民している第1世代なんだけど、泥臭さを感じない。
巽:アジア系アメリカ文学をしっかり意識した『紙の動物園』とかね。
小谷:そうそう。英語文学として洗練されている。いわゆるグローバル対応だと思います。ローカル性というのが、ただ単に土着でローカル色があるというよりは、一旦グローバリゼーションで世界に出ていって、なおかつ客観的なローカル性を再発見している感じ。トランスローカル性を持っているって言った方がいいかもしれない。外の世界の情報によく通じているし、一方で海外でも教育を受けてるし教養としてももちろん知ってる上で、だけどそれで客観的に自分達の土壌を見るっていう感じです。そういう中国文学がかなり出てきてます。
巽:ケン・リュウとは一度同じパネルに出たことがあるけど、彼の頭の中には西洋文学史や欧米思想史が全部入ってる。大変なインテリです。
小谷 :法律関係のことをしているんだよね。
巽:パネルでの彼は、シェイクスピアの時代から伝統的なナラティブがあるけどそれがポストモダンになるとこのように変容してこうなってってとか、パーっとまくし立てるわけですよ。
小谷:現代思想的なことも結構テキパキ饒舌に語ってました。西洋におけるポスト・モダニズムはこうだよね、みたいな。
巽:まくし立てるんだけど、大体正しいのね。
小谷:にも関わらず、その目で自国の中国をクールに見てるんですよ。
巽:それでケン・リュウの一番有名な『紙の動物園』というのは、アメリカの白人男性のエージェントがついてるんだけど、彼と話すと開口一番、「読んで泣いたか」って言うわけ。つまり、自分が泣いてるわけですよ。「泣いた体験」をみんなと共有したいという欲望が生まれるような小説なのね。だからさっきのBTS人気みたいな感じかも。
小谷:素晴らしい。素晴らしい。これは移民するっていうことで起きる世代間の断絶を描いてますね。移民の状況からくる目線でね。ベトナム戦争帰りのアメリカ人男性が現地の女の人を連れてきて妻にする。でもそのお母さんは英語が喋れない。
巽:そう、コミュニケーションができない。
小谷:生まれた子供はアメリカの教育を受けるから英語を喋るのだけど、お母さんの言葉は分からない。
巽:それで紙の虎をお母さんが折るんだ。
小谷 :紙でね、折り紙で。
巽:動物を作るわけ。そうするとそれが動き出すんですよ。それがコミュニケーションツールになる。
小谷:息子はお母さんの泥臭さが大嫌いで本当に受け入れられない。何こんな女はみたいな感じで見ていたのに、お母さんが亡くなっちゃった後もう一回見直す。その時にその動物たちがね、本当にファンタスティックに動く。紙の動物たちの不思議な力はお母さんの母国の文化の象徴です。彼女は言葉が喋れないけれど愚かではなく、異なった文化の人なんです。異なった文化そのものが西欧からは侮蔑の対象とされているかもしれないけれど、¬異文化は実は異世界の厚みがあり魅力的でもある。それを背景にした母親への思慕の情と、異文化へのオリエンタリズムと、アジアヘイトが混ざり合うわけ。哀しいし、どうしようもないし、でも目が開かれることへの優しさもあって複雑ね。
巽;アジア系アメリカ人の移民史全般を射程に入れているから、第1世代とか第2世代のずれがあるんだけれども、そうしたアジア系アメリカ文学のお約束に対して、ケン・ リュウはSFやファンタジーのフォーマットで切り込んでるのが新鮮なんですよ。それは例えば日系女性作家ヒサエ・ヤマモトの「十七文字」”Seventeen Syllables”(1949年)が俳句好きの一世の母とそれを理解しない二世の娘の世代間落差を描いてますが、そういうアジア系アメリカ文学の泣かせどころを巧みに取り込んでるんですよ。移民文学の泣かせるどころ自体が、もうフォーミュラ化してるからね。
小谷:やっぱり家庭内で英語ができない違う人たちが共存している世界で、新しい子供たちは喋れない人たちをバカにするっていうか侮蔑するんだけど、しかしずっと年をとってみると何か非常にその悲哀・悲しみとか、言葉が通じないことに対するある種の複雑な気持ちを持つっていう。やっぱりそういう時間の流れの中で世代間の断絶について考えていくっていう。それはカナダのThe Kappa Childを書いた…
巽:ヒロミ・ゴトウですね。
小谷:熊本出身の女性作家で、カナダに移民しているかたですね。カナダの女性作家ではこの種の家庭内断絶テーマを何人か書いてますね。アジア系の移民が多いせいかな。
戦後アメリカ国内における韓国系・アフリカ系の衝突
大和田:アニメ映画のElemental(2023年公開、邦題:マイ・エレメント)もそういう話ですよね。あの作品も韓国系が監督ですが、登場人物では親世代は英語が喋れなくて、子供の世代はアメリカで育ってるからどちらかというと韓国語の方が苦手で。そうした中で、韓国系のカルチャーをどのように受け継いでいくかが一つのテーマになっています。今の話でいうと、日本や韓国など東アジアとアメリカの関わりって共通する部分とそれぞれの国の独自性がある。たとえば、ベトナム戦争との関わり方も国によって濃淡がありますよね。本にも書きましたが、K-POPってもともと1992、3年ごろに成立したと言われてるんですが、92年ってロス暴動の年じゃないですか。あの時、もちろん最初はアフリカ系の暴動として始まるんだけど、途中からアフリカ系と韓国系のコミュニティーが敵対し始めますよね。日本でもよく、韓国系の住民が自分たちの店を守るために略奪者に向かって銃を撃つ映像が流れていましたが、なぜあの人たちが銃の扱いに慣れていたかと言うと、彼らは朝鮮戦争やベトナム戦争に従軍していたからなんですよ。彼らはアメリカの戦争に韓国人として参戦し、戦後、豊かさを求めてアメリカに移民した。でもロス暴動が起きて、韓国自体も経済発展を遂げていたので、その一部が韓国に逆移民というか、帰国したようなんですよ。そしてその一部が韓国の音楽業界に関わるようになる。92、3年のロサンゼルスといえば、ギャングスタ・ラップの全盛期なんです。だから韓国の音楽業界にとっては、突然本場のギャングスタ・ラップを熟知した韓国系アメリカ人が入ってきたということで、そこで音楽業界にも大きな変化が起きた。それこそがK-POPの土台になったわけで、だからK-POPって基本はヒップホップなんですよ。日本と違ってどのアイドルグループでもラップ担当がいるじゃないですか。つまり、K-POPの成立に韓国とアメリカの戦後史そのものが凝縮されているんです。

巽:朝鮮戦争ってまだ終わってないわけでしょ。
大和田:そう、今でも兵役がありますよね。うちの娘も含めて、世界中のBTSのファンは定期的に冷戦について考えざるを得ない状況に置かれている。
佐藤:なぜか戦争の後って、有色人種のベテランというのは迫害の対象になるんですよね。第2次大戦後の黒人兵がそうですよね。
大和田:韓国人が黒人に対する差別的な感覚を身につけたのは、朝鮮戦争の時に駐留したアメリカ軍がアフリカ系ばかり最前線に送って、白人が割と安全なポジションに配置されるのを間近でみたからだとある研究に書いてありました。僕は最近、冷戦の表象としてのアイドルというテーマをずっと考えていて。だってエルヴィス・プレスリーも人気絶頂期に兵役でドイツに駐留しますよね。あれも東西ドイツの問題ですし、アイドルと冷戦というのはひとつテーマになるのではないかと。
巽:それは面白い。
大和田 :みんな兵役に行っちゃう。
佐藤:そうか。兵役とポップスか、いや、それは面白いね。
戦争と“Color”
巽:ちなみに、ニューヨーク学院では五月に必ず遠足の日があるんだけど、今年行ったのは、ひとつはハドソン河畔の全米料理大学(Culinary Institute of America)略称CIAのTシャツまである(笑)。
小谷:全然秘密スパイ組織の拠点とかじゃなくて料理学校でした~(笑)
巽:いやすごく良かったよね。それでそのすぐ近くにFDR(=フランクリン・デラノ・ローズベルト第 32代大統領)の家があって、そこにも寄ったんだけど、ものすごく良かった。初老のガイドの方が色々説明してくれるんだけど、彼がはっきりと「やはりFDRが日系強制収容所を作ったのは間違った政策だった」と断言していた。
小谷:我々日本人系というか、日本系の学校の生徒が訪れたというので、多分意識してんだと思うんですけど。
巽:FDRの過ちは、のちの1980年代、ロナルド・レーガン第40代大統領が謝罪することになる。
大和田:あれは収容所を経験した日系人に対して政府が賠償金も払ったんですよね、たしか。
巽:やはり強制収容所というのは黄禍論の産物だったんだよね。だってドイツ系アメリカ人とかイタリア系アメリカ人は普通に兵隊やってるんだから。
小谷:日本人だけは囲い込まれて収容所に行かされた。
巽:やはり文学研究やる際に、作家の生地というか聖地にはやはり行った方がいい。我々たまたまもう12年ほど前だけど、シカゴの会議のあとにカート・ヴォネガットの生誕地のインディアナポリスに行ったことがあるんだけど、インディアナポリス行って分かったのは、もう全部ドイツ系の町なんですね。ヴォネガット家は代々お金持ちで由緒正しくて、お父さんもおじいさんもいろんな建物作って、そういういいところの坊っちゃんで、しかも次男だったのがカートだったわけですよね。だからドイツ系でありながら第二次世界大戦に従軍してドイツへ派兵されるというのは、いかに辛い経験だったか、想像するにあまりある。ドイツ系の自分が母国であるドイツを敵と見做して戦わなきゃならないんだからね。そのあたりの辛さは『スローターハウス 5』(1969年)Slaughterhouse-Fiveで書かれてるけど、ドレスデンで捕虜になってる間にアメリカ空軍による大爆撃があって、自分の属してる国に殺されるかもしれないという、もうとんでもない不条理ね。この不条理というのは、私やはり中学ぐらいの時に読んだだけじゃ分かんなかったですね。捕虜生活も爆撃も辛いだろうと思ったけど、本日のテーマに合わせて言えば、自分と同じ肌色の民族と殺しあわなくちゃならないという存在論的な危機までは、中学生には伝わらなかった。ニューオーリンズに今第二次世界大戦後博物館というのがあって、第二次世界大戦のアメリカ人特有の語り方が、展示見ると切々と分かってくるのね。坂手洋二さんなんか、カンカンになって怒っちゃう。でもね、一応アメリカン・スタディーズやってると、アメリカ人はこれぐらいのことは言うよなと思った。結局肝心なのはナラティブなんだよ。どういうナラティブかというと、やはりまず巨大な地図を出すわけで、そうすると確かに戦時中の日本がどんどん増やしてった植民地の数は膨大でとてつもなく多くて、他国を圧倒しているのが実感される。
小谷:というのは、日本はナチス同様すごい強大な悪の帝国だという前提がまずバーンと出る。
巽:それで、アメリカ人はとても怖かったと。こんな強大な国に自分たちはもう負けるんじゃないかと思ったので、もう嫌で嫌でしょうがなかったけれどイギリスと手を組んだ、というナラティブを織り紡ぐ。
佐藤:だからキャプティヴィティ・ナラティブでの異人恐怖の宣伝と同じですよ。
小谷:異世界ファンタジーでも定型になるほど愛されるパターンかな。それで最終的には原爆で勝利したと。最初の日本がいかに大きくて巨大な帝国だったかというのがナラティブとしてあるから、これに勝つには仕方がなかったのだ、と。
巽:アメリカ人はこれは自分たちが負けるって思ったというのが全ての前提にある。それを証明する地図の迫力が凄まじい。
小谷:君はアメリカ兵士の1人なんだというステッカーを持たされて、その個人的体験を途中機械で再現しながら、つまりその戦争に参加しながら、その強大な国と戦うという演出です。わたしのステッカーの兵士は途中戦死しました。今の日本だと、日本ってこんな小さい島国なのになんであんな馬鹿な戦いしたの?みたいな感じになってるじゃないですか。違う。あの博物館ではそうではない。
巽:今は原爆を投下した方が悪いとかね、みんなそういうことになってるけれど、でも当時はやはりパールハーバーの方が悪いと、そういうことになっていたし。
小谷:強大で邪悪な帝国だから、奇襲などというあんな悪いことしたんだと。
巽:パールハーバーだけじゃなく、あんなにたくさん植民地持たれたらこれはもう適うわけがない、というナラティブ。
大和田:強大な帝国はたしかにそうですが、敵わないわけがないようにも思いますが。
巽:いや、そういうナラティブですから。
佐藤:出だしをどこにするかというのは大きいですよね。
巽:坂手さんだけじゃなく、あの博物館展示を観てがカンカンになる日本人は多いみたいね。
小谷:怒るより心が折れたわ。自らの戦いの正当性を主張するためにやはりそういう風になってる。あの説得力は恐ろしい。
巽:だからもちろんあの落としどころは原爆投下が正当だったというのが文字通りの落としどころなんだから。
小谷:戦いの火蓋は日本が追い詰められていたからだという説もあるけれど、けしてそうじゃない。
巽:アメリカは怯えてた。負けるかもしれないと思ってたんだ。そういう展示なのよ。
大和田:その博物館がニューオーリンズにあるのが謎ですよね。ニューオーリンズといえば第一次世界大戦で軍港になったのが有名ですよね。港の赤線地帯で演奏していたジャズ・ミュージシャンが、軍港になったことがきっかけで職を失い、全米の都市に移住したことでジャズが全米に広まった、というのがジャズ史上のナラティブです。
巽:ところが、今じゃそこの最大の名所になっていて、ルイ・アームストロング空港を降りると、壁中に所狭しと「第二次世界大戦博物館」のポスターに次ぐポスターが貼りまくられてるんだ。
小谷:子供連れの家族がたくさん訪れていて、みんなしっかりと学習するわけです。
大和田:それでちょっと思い出したんですが、先にお話しした通り、コロナ禍でずっとハーバード大学のデータベースを閲覧していたときに、100年前のスペイン風邪のことを調べたんです。興味深いのが、敵のドイツ軍と病原菌を結びつける記事が多いんですよね、GermとGermansみたいな。あのときに思ったのは、僕らも知識としては1918年にスペイン風が流行したのは知っていたけど、それが具体的に社会にどのように影響を及ぼしたかについてはわかっていなかった。それがコロナ禍を経験することで、具体的に想像できるようになったんです。例えばスペイン風邪が流行した時期にレコードの売り上げが爆発的に伸びるんですよ。そのことも知ってはいたんですが、パンデミックになってライブハウスに人が集まらなくなって、それでレコードという新しいメディアが注目されたという、二つの歴史的事実をようやく結びつけることができた。当時の新聞記事にも、劇場ではマスクをしなければならないとか、コロナ禍と全く同じような対策が取られていたことが書かれています。スペイン風邪は、一説にはカンザス州の軍の施設で始まり、それが第一次世界大戦にアメリカが参戦したことでアメリカ兵を通じて世界に広まったともいわれている。それがさっきのニューオーリンズが軍港になったことと微妙に重なるのは、世界最初のジャズ録音を残したオリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドのメンバーが、スペイン風邪で亡くなってるんですよね。だからコロナ禍の時に、「カンフルー」とかアジア系への差別が強まりましたけど、スペイン風邪の時はむしろドイツ差別が強まった。音楽界では、もうドイツの作曲家の曲は演奏すべきではないという人が出てきたり。
巽:ドイツ差別ですよ。でもイエロー・ペリルってね、最初はドイツ人が発明したんだよね。
佐藤:あとドイツで迫害されてきたユダヤ系が、今度は黒人のグループのレコード会社を立ち上げて、ビリー・ホリデイのレコード出したりとかするんですもんね。
アメリカ大統領選(2024年)の混戦
巽:なかなか複雑。あとは話題は…アメリカ大統領選。
大和田:それどころじゃなくなりましたね。
巽:凄まじいことになってますからね。
小谷:バイデンがコロナかかったというニュースが今日出ましたね。
佐藤:色々逆境ですね。
小谷:片方は撃たれて写真撮られて、片方はコロナで。
巽:だからますます分かんなくなった。前の時は、私はもうヒラリーが勝つと思ってた。あのメディアもそういう方向だった。だから今回も読めない。
大和田:バイデンにこだわってますね、民主党は。
巽:対抗馬が最初からいなかった。そうなんだ。カマラ・ハリスじゃいけないというじゃない。
小谷:うん。多分保守層がすごく強いので、黒人の女性はまだ早いって言うんじゃないかなって。でも私たちの感じでは大統領と副大統領を逆にすればって思うんだけどねえ。やはりカマラさまでしょって思うんだけど、保守層ってやはり根強くて、また今回の都の地知事選もそうなんですけど保守層の強さというのはすごいですね。
佐藤:すごいですね。だから民主党の中の軋轢というか、バランスの対立があって、やはりとてもそういう本当にリベラルな人たちと保守層的な民主党員との間のバランスの取り合いがちょっとデリケートでね、昔からそう。
巽:だから今ね、バイデン降ろしを民主党の中で言われてるけど、だって共和党の中でトランプ批判というのもすでにあったからね。
小谷:散々ね、やられましたよね。だからもうぐじゃぐじゃ。
巽:ちょっと流れ込むんじゃない。
佐藤:でもああいう風に、右耳でしたっけ。正面向いてれば確かにこめかみに当たっていて、やはりかなり正確に撃ってたんですよね。
小谷:127メートルでしたっけ。
大和田:しかも犯人は建物を登ってるところを見られているんですよね。
巽:射殺されちゃったからね。
佐藤:だから日本の安倍首相が撃たれた時は日本だからそういう対策が甘いところもあったのかなと思ったけど、やはりアメリカでも起きる時は起きるんですね。あれでさすがのトランプも自分はもう死んでるはずだったって言ってるのは、やはり自分の身に起こるといろいろあるでしょうね。だから今トランプに一種のコンバージョン的なこと起きないのかなと。なにかこう、自分は死んでたはずだ、それで生き直す。だからトランプが変わるっていうことも起こるのかな?
大和田:生まれ変わっていい人になるとかですか?
佐藤:これからね、自分は死にかけたわけだから、それでもやはりライフル協会とかを相変わらず支援するのかなとかね。
大和田:でもいかにもアメリカらしいと思ったのは、ニューヨーク・タイムズでしたっけ、トランプがガッツポーズする背後に星条旗がはためいている写真。なんともいえないほど絵になると思って。
小谷:写真がすごかったですよね。奇跡の一枚かな。
巽:だからね、あのポーズを決めたくて仕組んだやらせじゃないかっていう説もある。
大和田:完璧な構図で。それで星条旗ははためいてって。
巽:そうなんだ、星条旗があるんだよね。
佐藤:合成したみたいなね。
巽:写真として名作。
大和田:あの写真はリベラルなニューヨーク・タイムズでも抗えないですよ。
小谷:あれを見てやはり奮い立った保守層を考えると、ちょっとムカつく。あれを見て白人家父長制の断末魔が。
大和田:あれで勇気をもらったらダメだと思いつつ、エモーショナルな写真ではありますよね。
巽:だからちょっとまだ読めないんだ。まだ時間があるから。
大和田:トランプの一期目のとき、マイケル・ムーアとリチャード・ローティが言ったことがよく参照されましたよね。民主党が労働者の党からアイデンティティ・ポリティクスの党になった──このことを僕はブルース・スプリングスティーンの党からテイラー・スウィフトの党になったとたまに話すんですが──ことで白人男性労働者が右傾化してトランプを支持したんだと。だからブルース・スプリングスティーンは生涯民主党支持かもしれないけど彼のファンはもしかするとトランプ支持者になっているかもしれない。それで民主党が、それこそテイラー・スウィフトのようなある種の華やかさを体現する党になっているのだとしたら、民主党は、やっぱりバイデンだけが白人労働者に語れる存在なのだと思ってるかもしれないですよね。ハリスだと白人男性労働者に支持されないのではないか、それは2016年と同じ轍を踏むことになるのではないかと。バイデンは割と労働者ともガラの悪いトークができる人ではあるので。
巽:一方でね。トランプがテイラー・スウィフト批判をしてるじゃないですか。
大和田:テイラー・スウィフトは昔、アーリア人の女神と呼ばれたり、保守派のアイドルだった時期もあるんですよ。
巽:今アメリカですごいよね、テイラー・スウィフト。雑誌とかもうバンバン表紙になってる。
大和田:ほとんど陰謀論ですよね(笑)。テイラーは今、付き合っている相手がアメリカンフットボールのスター選手なんですが、その彼が出場するスーパーボウルの日程が、テイラーの東京ドームの4デイズ公演の直後らしく、ライブを終えたあとに飛行機に乗って間に合うかどうかが大きな話題になっています(笑)。まあ本当にどうでもいい話ですが、テイラー・スウィフトの歴代彼氏を把握しているものとしては、ずっと根暗な文化系男子が続いて、でも最後の最後にアメフトのスター選手と付き合ったというのが、なんともいえないというか。それはやっぱりかっこいいですよね、としかいえないです。
副大統領候補(当時)のJ・D・ヴァンス氏とカマラハリス氏について
巽:あとやはり争点になるのはトランプの副大統領候補のJ・D・ヴァンス。彼の2016年の自伝『ヒルビリー・エレジー』はアメリカ学会でも話題になったな。ホワイトにも色々あるんです。プアホワイトという色があるわけだ。
大和田:最初トランプ批判してましたよ。
佐藤:そうですよね。どっちかっていうと、だからバイデン側の知り合にいそうな、ラストベルト出身みたいなのかと。
巽:丸め込まれた。
佐藤:ね、急に変わったんですよね。
巽:映画にもなったでしょ。
佐藤:映画もありますね。書籍の日本語訳もね。
大和田:あまり評価高くなかったですよね。
巽:うん。でも分かりやすいよね。あれは本当に。ヒルビリーはアパラチアに住んでるプアホワイトだから、アメリカンドリームからも疎外されてるんです。そもそも移民がアメリカに来るのは成功の夢を抱いているからで、アメリカならば、仮にある州で挫折して失敗しても別の州に行き、自分のアイデンティティを立て直せばよい。だけど、『ヒルビリー・エレジー』で書かれてることは、あまりにも貧しいプアホワイトは、行きたくても財力がないため他の州にも行けない。
大和田:ヴァンスに『ヒルビリー・エレジー』を書くように進言して、実際に文芸エージェントを紹介したのはイェール大ロー・スクールのエイミー・チュア(蔡美儿)という中国系の教授。東アジア系の母親の強烈な「教育ママ」っぷりを書いた『タイガー・マザー』という本がものすごく話題になったんですが、彼女自身は中国系の移民家族のもと、結構いじめられたりしながら育ったようです。ものすごく育ちのいい白人のお坊ちゃん、お嬢さんがひしめき合うイェール大ロースクールで、JDヴァンスとエイミー・チュアは少数派同士として共感し合ったようなんですよね。だから『ヒルビリー・エレジー』という作品のバックグラウンドには、プアホワイトとアジア系移民というマイノリティーの結びつきがあるんですよ。
巽:ちょっと大統領選は今の段階じゃ先は読めないね。ここのところ随分カマラハリスがツイートしてますね。
大和田:まあまあ評価上げてるみたいなんですよね。
巽:バンバン語ってますね、今ね。
大和田:カマラ・ハリスは検察官出身なので実は黒人男性に人気がないんですよね。アフリカ系の男性をどんどん投獄した張本人だったので。ブラック・ライヴズ・マター運動で黒人の大量投獄があらためて問題になったりして、ハリスの人気にも少し影響が出たらしいんですが、でも最近また評価が高くなってますよね。
佐藤:インド系の女性で大統領っていったらすごいですよね。
巽:11月が楽しみ。
佐藤:今日は本当にお忙しいところ色々ありがとうございました。日本人を扮するミンストレルショーでは日系をある意味で文化的搾取をして、いままでは黒人を白人が演じていたものが今度は黒人がアジア人を演じるという、これもニューヨークが舞台だったということを大和田先生の論文で知りました。これは文学史的な関連でいうと、ウォルト・ホイットマンが日本の遣米使節団が来たのを見てそれで詩(“A Broadway Pageant”)にしてることに関わりますね。そこでちゃんとジャパニーズじゃなくてニホン(Niphon)という言葉を使っています。でもあの頃のアジア観というのは、やはりまだ雑多なイメージで。つまりウォルト・ホイットマンの詩の中でも「アダムの子孫たち」(Children of Adam)と言った場合には、ざっくりエデンの園がアジアにあったというイメージなので、おなじことは詩「インドへの道」(“Passage to India”)でもインドも結局ざっくりアジアのことなんですよね。別にインドのことを歌ってるわけじゃなくて、すごく大雑把なアラブも東南アジアも区別がないような中なかに日本も入ってたわけですね。だから19世紀ぐらいの時のそういう雑多なイメージは時間が経ってみると、集合的無意識みたいな形で出てくるのかもしれません。そういうことこそ政治的・経済的な分析では見えないようなもうちょっと古いところで、文学者だから見えるようなアメリカの人種の古層みたいなところが見えてくるかなという、そういうことも考えさせていただきました。今日は大統領のホットな話題も最後非常に広いスパンで聞かせていただき楽しいひとときでした。ありがとうございました。
──本日はありがとうございました
投稿:五關優太